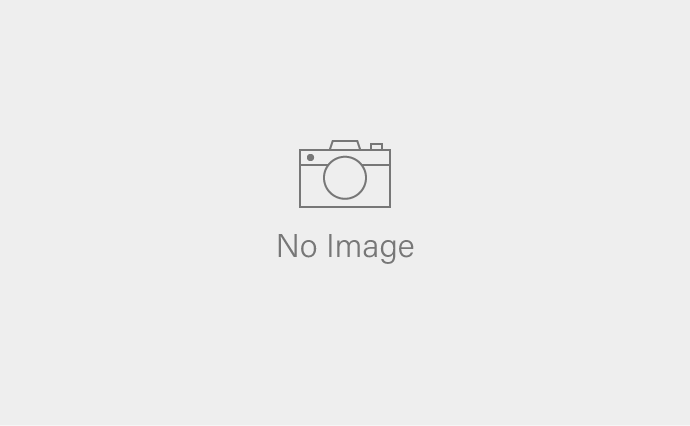ブログの記事を書くとき、毎回のように敬体(です・ます調)か常体(だ・である調)にするか悩んでいます。
文章を書くことは得意ではありませんが、最低限の知識を身につけないと、恥ずかしい思いをすることにもなりかねません。
調べてみると、他のブロガーの方々も同じように悩んでいるので、皆さんの結論をまとめつつ、私も自分なりの結論を出すためにこの記事を書いてみました。
はじめに、敬体と常体のメリット・デメリットについて、Gemini先生にまとめてもらいました。
敬体(です・ます調)のメリット・デメリット
メリット
丁寧で信頼感のある印象を与えられる
「です・ます調」は、相手に対する敬意を示す形式です。読者に対して丁寧な言葉遣いをすることで、書いている人の人柄が誠実で礼儀正しいという印象を与えられます。これにより、読者は安心して記事を読み進められ、ブログ全体への信頼感が高まります。特に、専門的な情報やアドバイスを提供するブログでは、この信頼感が非常に重要になります。
読みやすく、多くの人に受け入れられやすい
「です・ます調」は、日本語の文章として最も一般的で標準的な形式です。このため、幅広い層の読者にとって違和感がなく、読みやすいと感じてもらえます。特に、インターネットにあまり慣れていない方や、特定の専門分野に詳しくない方にもスムーズに内容が伝わりやすいです。
堅苦しくなりすぎず、親しみやすさも保てる
「です・ます調」は、丁寧でありながらも「〜だ」「〜である」といった常体と比べて柔らかく、親しみやすい雰囲気を持っています。読者との距離が縮まり、まるで会話しているかのような感覚で読んでもらえるため、エンゲージメントが高まります。
メリットのまとめ
ブログを「です・ます調」で書くことは、読者との間に信頼関係を築き、読みやすさを確保し、親しみやすさも両立できるという大きなメリットがあります。ブログのテーマやターゲット読者にもよりますが、多くの場合は「です・ます調」が効果的です。
デメリット
記事によっては冗長に感じられる
「〜です」「〜ます」という形は、常体(「〜だ」「〜である」)と比べて文字数が多くなります。そのため、情報が凝縮された記事や、読みやすさを重視するリスト形式の記事などでは、文章が間延びして冗長に感じられることがあります。特に、素早く情報を把握したい読者にとっては、少しもどかしく感じるかもしれません。
強い主張や断定的な表現がしにくい
「です・ます調」は丁寧で柔らかい印象を与える反面、強い主張や断定的な表現には向いていません。「〇〇がおすすめです」のような表現はできますが、「〇〇をやるべきだ」といった強い言い回しは、です・ます調では馴染みにくいです。読者に力強く訴えかけたい場面では、常体の方が効果的な場合があります。
専門的な分野では軽すぎる印象を与えることも
学術的な内容や、硬派なテーマを扱うブログの場合、「です・ます調」だとやや軽薄な印象を与えてしまう可能性があります。特に、論文や研究結果を引用するような記事では、常体の「〜である」の方が信頼感が増し、文章全体に重みが出ます。
デメリットのまとめ
「です・ます調」は、親しみやすさや丁寧さを出せる一方で、簡潔さや力強さに欠けるというデメリットがあります。ブログのテーマやターゲット読者、そして記事ごとの目的に合わせて、敬体と常体を使い分けることが、より効果的なブログ運営につながります。
常体(だ・である調)のメリット・デメリット
メリット
簡潔で力強い印象を与えられる
「だ・である調」は、「です・ます調」と比べて文字数が少なく、文章がすっきりと簡潔になります。これにより、読者は情報を素早く把握でき、記事全体にスピード感が生まれます。特に、事実や結論を明確に伝えたいとき、この文体は非常に効果的です。また、文章に力強さや説得力が増し、読者に強い印象を残すことができます。
専門性や信頼性を高められる
「だ・である調」は、学術論文や専門書などで多く用いられる文体です。このため、ブログで使うと、記事の内容が専門的で信頼性が高いという印象を読者に与えることができます。特に、特定の分野に関する深い知識や分析をブログで発信する際に、この文体は権威性を高めるのに役立ちます。
表現の幅が広がる
「だ・である調」は、断定的な表現や、自分の意見を強く主張したいときに適しています。「〇〇が重要である」「〇〇すべきだ」といった表現を使いやすいため、読者の行動を促したり、議論を提起したりするような記事に向いています。
メリットのまとめ
「だ・である調」は、簡潔さ、力強さ、そして専門性をブログに持たせたい場合に大きなメリットがあります。一方、「です・ます調」のような親しみやすさには欠けるため、ブログのテーマやターゲット読者に応じて使い分けることが大切です。
デメリット
高圧的で冷たい印象を与えやすい
「だ・である調」は、読者と対等な目線ではなく、やや上から目線で一方的に語りかけているように感じられることがあります。特に、個人の体験談や趣味を綴るブログなど、親近感を重視する内容では、読者が突き放されたような印象を受け、読者との距離が遠くなってしまう可能性があります。
親しみやすい表現がしにくい
「です・ます調」では、「〜ですよね?」「〜と思います」といった、読者に語りかけるような柔らかな表現が自然にできます。しかし、「だ・である調」ではこうした表現がしにくく、全体的に硬く事務的な印象になりがちです。顔文字やスラングなど、くだけた表現とも相性が悪いため、人柄を伝えたいブログには向いていません。
記事によっては読みにくい
「〜だ」「〜である」という語尾が続くと、文章が単調になり、リズムが悪くなることがあります。また、「です・ます調」と比べて漢字が増える傾向にあるため、記事によっては読みづらさを感じる読者もいます。
デメリットのまとめ
「だ・である調」は、記事に説得力や権威性をもたせたい場合に有効ですが、読者との心理的な距離が生まれやすく、親近感や共感を得にくいというデメリットがあります。ブログのテーマや目的に合わせて、どちらの文体を選ぶか検討することが重要です。
記事ごとに敬体と常体を使い分けるのはおかしいのか?
他の方々の文末表現をどちらにするかという記事を見ていると、常体(だ・である調)のほうが多いのかなと感じますが、それぞれ記事ごとに敬体と常体を使い分けるというのは、おかしいことなんだろうか?というのをGemini先生へ質問してみました。
ミトス
ブログの記事ごとに敬体と常体を使い分けるのはおかしいですか?

Gemini
ブログの記事ごとに敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)を使い分けることは、全くおかしいことではありません。むしろ、読者の読みやすさを考えた、非常に効果的なテクニックです。
記事ごとの使い分けが効果的な理由
ブログ全体で文体を統一するのも一つの方法ですが、記事ごとに使い分けることで、それぞれの記事の目的に合った最適な印象を読者に与えることができます。
専門的な解説記事やニュース記事
客観的な事実や深い分析を伝えたい場合、常体(だ・である調)を使うと、記事に信頼性と説得力が増します。読者は情報を素早く、的確に理解できます。
個人的な体験談やレビュー記事
自分の考えや感想を親しみやすく伝えたい場合、敬体(です・ます調)を使うと、読者との間に親近感が生まれ、共感を得やすくなります。
ハウツー記事やチュートリアル
読者に丁寧な語り口でステップを説明したい場合、敬体(です・ます調)が適しています。一方、手順を箇条書きで簡潔に示したい場合は、常体(だ・である調)の方が読みやすいこともあります。
注意すべきポイント
同じ記事の中で文体を混ぜない
一番大事なのは、一つの記事の中では文体を統一することです。記事の途中で「です・ます」と「だ・である」が混在すると、文章のリズムが崩れ、読みにくく、プロフェッショナルでない印象を与えてしまいます。
ブログ全体で一貫した「トーン」を意識する
記事ごとに文体を使い分けても、ブログ全体の「トーン」は一貫していることが理想です。例えば、全体的に親しみやすいブログなのに、突然硬い常体で書かれた記事があると、読者は戸惑ってしまうかもしれません。文体を変えても、ブログの雰囲気や著者の個性は変わらないように意識すると良いでしょう。
ブロガーの方々の記事
文末表現について書いているブロガーの方々の記事を紹介していきます。
文章の「常体」と「敬体」の使い分けと考え方を現役ライターが解説
株式会社アワード
文章を書くとき語尾をどのように使い分けていますか? 日本語文には「常体」と「敬体」があります。先ほどの冒頭文を常体にすれば、「文章を書くとき語尾をどのように使い分けているだろうか」。ちょっと印象が変わりますよね。今回は、ライティングにおける常体と敬体について解説します。
ブログの文体は「です・ます」調と「である」調とどちらがいいのか?
イタリア音楽サロン ヴェルヴェッティーノ
このブログ「です・ます」調で書き始めたけど、実は「である」調のほうが書きやすいんだよね・・・
果たして、「です・ます」調or「である」調どちらの文体でブログを執筆すべきか、読む側と書く側両方の視点からメリット・デメリットを考察してみました。
常体+敬体=コードスイッチ話法。
Note Bwさん
作文の授業では、いわゆる「だ、である」の常体と「です、ます」の敬体の統一が推奨される。ひとつの作文のなかに混在していると、赤ペンを入れて直されてしまう。しかし、実際のところどうだろう。適度に混在させて使ったほうが、いい雰囲気にならないだろうか。
僕の結論は
僕の結論は、記事の内容によって敬体と常体を使い分けていくということに決めました。
ハウツー記事は敬体(です・ます調)で書いていきます。個人的な体験談やレビュー記事については、親近感や共感を得やすいとされている敬体ではなく、書きやすい常体「だ・である調」で書くことにしました。
文語体をうっかり使うことは少ないと思いますが、話し言葉をそのまま書くのではなく、書き言葉にするように徹底していきたいと考えています。ただ、これは自分にとっては少しハードルが高いと感じています。
だからといって、常識から外れた文章作法だと、読者に不自然な印象を与えてしまうかもしれませんし、意識しすぎると個性がなくなってしまうような気もします。

ミトス
本音を言えば、文体を意識してしまうと書くのが遅くなるし、自由に書きたい。。。
日本語は本当に奥が深くて難しいですよね。学生の時は何も考えていませんでしたが、今こうして記事を書いていると、文体が正しいかどうかを意識してしまいます。
文体の知識がなくても、ChatGPTやGeminiに聞けば修正してくれるので、深く自分で学ぶ必要がなくなってきていると感じることもありますね。
Gemini先生に添削してもらったら
前述した僕の拙い文章をGemini先生に添付や張り付けをした後で「敬体の口語体で、書き言葉のルールに合わせて添削してください。」とお願いをします。
そうすると下記のように、見事に添削してくれます。
さらに言えば、文語体をうっかり使ってしまうことは少ないかもしれないが口語体で書いて、話し言葉を書き言葉にするように徹底していきたいと思ってはいるが、僕自身にとっては敷居が高いと感じています。
↓
文語体をうっかり使うことは少ないと思いますが、話し言葉をそのまま書くのではなく、書き言葉にするように徹底していきたいと考えています。ただ、これは自分にとっては少しハードルが高いと感じています。
ポイント
- 「〜かもしれないが〜」という話し言葉の表現を整理しました。
- 「思ってはいるが」を「考えています」とすることで、より書き言葉らしい丁寧な表現にしました。
- 「敷居が高い」を「ハードルが高い」とすることで、意味合いをより明確にしました。
かといって、常識外れな文章作法だと醜態を晒してしまうことにもなりかねないし、意識していくとなると個性が無くなるような気もします。
↓
だからといって、常識から外れた文章作法だと、読者に不自然な印象を与えてしまうかもしれませんし、意識しすぎると個性がなくなってしまうような気もします。
ポイント
- 「〜なりかねないし、〜」という表現を「〜かもしれませんし」とすることで、丁寧な書き言葉にしました。
- 「醜態を晒してしまう」という強い表現を、「不自然な印象を与えてしまう」とすることで、より客観的な表現にしました。
日本語って本当に奥深くて難しいですよね。学生の時は何にも考えて無かったけど、今こうして記事を書いていると文体が正しくなっているか意識してしまいます。文体の知識が無くても、ChatGPTやGeminiに問いかければ修正してくれるので、深く自ら学ぶ必要性も無くなってきているとも感じますね。
↓
日本語は本当に奥が深くて難しいですよね。学生の時は何も考えていませんでしたが、今こうして記事を書いていると、文体が正しいかどうかを意識してしまいます。文体の知識がなくても、ChatGPTやGeminiに聞けば修正してくれるので、深く自分で学ぶ必要がなくなってきていると感じることもありますね。
ポイント
- 「〜って」という話し言葉を「〜は」に。
- 「〜何にも」を「何も」に。
- 「〜〜していると」という表現はそのまま使えますが、ここでは「〜していると、〜」とすることで区切りを明確にしました。
- 「〜〜ので、〜〜」という話し言葉を整理し、読点が適切な位置に来るように修正しました。
中には、指示した以外の部分で「醜態を晒してしまう」という表現を「不自然な印象を与えてしまう」へ変えられてしまうとようなこともありますが、自分の表現を残すかどうか判断すれば、個性を残しつつも良い文章へ仕上がります。
参考までにどうぞ!